VOC分析とは?顧客満足度の向上に役立つ手法、手順などを解説

現在は、VOC分析を実施することで、顧客満足度の向上などのメリットを感じられると言われています。しかしVOCとは一体どうするものなのか、導入方法や進め方がわからない企業も多いのが実情です。
そこで本記事では、VOC分析の手法や手順について詳しく解説します。また、実際にVOC分析を実施する際の注意点もあわせて紹介します。業務やマーケティングに役立ててください。
VOC分析とはなにか
VOCとは、「Voice of Customer」の略で、「顧客の声」のことを示す用語です。近年、SNSの発達にともない顧客が考えを発信することも増え、業務改善のヒントを内包するものとして注目されています。
VOC分析は、さまざまな場所で得られる顧客の声を収集・分析し、企業の活動に反映させます。顧客の声は、例えばコールログなどの問い合わせ、SNSのエゴサーチ、アンケートの実施といった方法で手に入れることができます。ただし、たくさんの声を収集するだけでなく、分析することで企業としての改善点を洗い出し、業務に反映させることが重要です。
関連記事:VOC(顧客・お客様の声)とは?分析するメリットやポイントを解説
VOC分析を実施するメリット
VOC分析は非常に注目されていますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。VOC分析を実施するメリットを解説します。
1.商品やサービスの開発・改善に活かせる
VOC分析の大きなメリットは、顧客の声を自社の商品やサービスの開発、および改善に活かせることです。
VOCを分析すれば顧客の声を分析し、要望を把握できます。既存の商品になにが足りないか、どのような機能や効果を求めているかなど、把握した要望を商品・サービスの改善や開発に活かすことで、リピート率の向上につながる可能性があります。
2.マーケティング戦略に役立つ
VOC分析を活用すれば、マーケティングの精度を高めることができます。
現在はSNSの浸透によって、以前よりもVOCを収集・分析しやすい環境になっています。顧客ニーズやターゲット層の傾向を読み取り、効果的なマーケティングを実施できれば、売上の向上にもつながるでしょう。
3.社員満足度の向上につながる
VOC分析の結果を適切に用いると、社員満足度のアップも図ることができます。
とりわけコールセンターなど、顧客の声のなかでも不満などのマイナスな感情をぶつけられてしまいやすい部署では、社員も士気を落としがちです。顧客の声のなかでも、感謝の声などプラスのものを現場に届けることで、コールセンターの存在意義を高められる可能性があるでしょう。
VOC分析の手法
VOC分析には、いくつかの方法があります。ここではVOCを収集するデータソースごとに、やり方、メリット、デメリットを解説します。
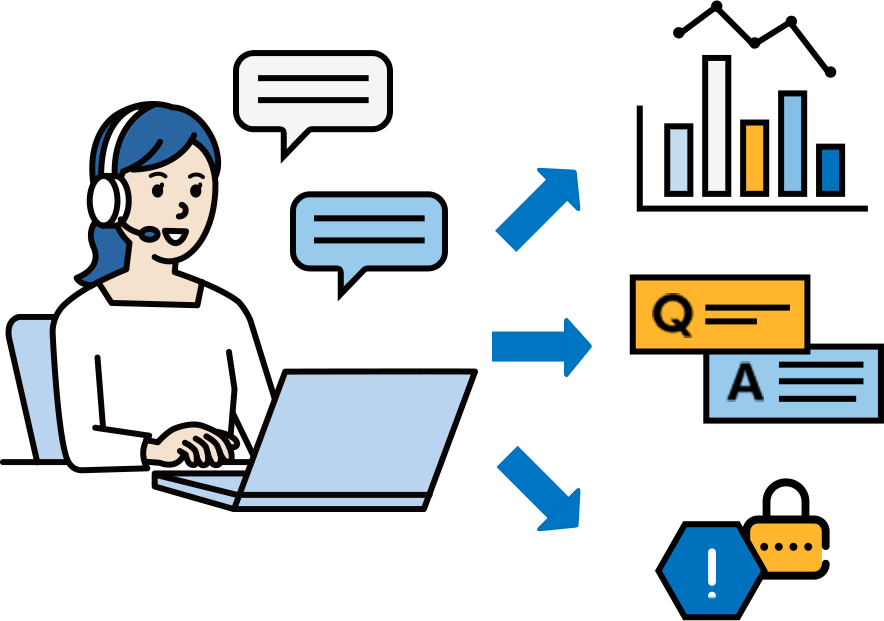
1.コールセンター
コールセンターは、電話で顧客の声を直接聞く方法です。直接、顧客とスタッフとが対話を行う形式ですが、一方で直接対面しないため、本音を聞き出しやすいのがメリットです。
また、コールセンターという場所柄、困りごとを抱えた顧客の方から連絡を受ける可能性が高く、顧客が具体的になにを困っているかを聞けるでしょう。
デメリットとしては自動録音機能や、システム環境の整備が必要になるため、コールセンターの設置にある程度の経費がかかることが挙げられます。
2.アンケート
アンケートは、ハガキやメールなどで実施されることが多いです。現在ではWebアンケートという方法もあります。
アンケートのメリットは、無記名で回答できるものであれば顧客の本音を聞きやすいことにあります。改善してほしいポイントなどのマイナス点だけではなく、現場への感謝なども聞けるかもしれません。
ただし、準備や実施、集計に手間がかかることはデメリットのひとつです。集計システムを導入するなど、手間のかからない方法を選択すると良いでしょう。
3.SNS
3つめはX(旧Twitter)、InstagramなどのSNSから情報を収集する方法です。
SNSは利用している顧客が本音を吐露しやすい場所で、非常に多くのVOCを集められます。AIなどのシステムと組み合わせることで、膨大なVOCの分析が実現するでしょう。
ところが、SNSを活用した情報収集にはデメリットもあります。真偽が定かでない情報を発信しているアカウントも存在するためです。センセーショナルな発信であっても、それが顧客の声として信頼を置けるものかどうかは常に気に掛けておく必要があります。
4.インタビュー
インタビューは顧客と直接対面して、企業側が知りたいことに対して質問する方法です。
メリットは、情報の精度が高いことです。アンケートのように書き表すことでニュアンスが変わることもなく、顧客の感じていることを細部まで聞き取りできるでしょう。
一方、デメリットは時間がかかることです。インタビューを行うことそのものにも時間がかかります。それだけでなく、顧客との日程調整が難しいのもポイントです。
5.問い合わせフォーム、メールなど
企業サイトなどに問い合わせフォームや、問い合わせ用のメールアドレスを用意する方法もあります。
この方法では、顧客が24時間いつでも問い合わせできるのがメリットです。企業側としても、調査にかかる費用を削減しやすいでしょう。
一方で、迅速な対応が難しい、話がややこしい場合に対応しにくいといったデメリットもあります。
VOC分析を進める手順
いずれかの方法で集めたVOCを適切に分析するには、いくつかの手順が必要です。ここでは、VOC分析を進めるための手順を解説します。

1.分析の目的を明確にする
まずは、分析の目的を明確にします。
商品やサービスについて、「改善や向上を目的とするのか」「事業戦略の策定のためにVOCを用いるのか」「スタッフのやる気を向上させるために使うのか」などを考えてみましょう。VOCをもとに営業ツールを作成したり、顧客へのアピールポイントを掴んだりすることもできます。
あらかじめ明確な目的を設定することで、どのような情報が必要か、どのような調査方法が適切かが判断しやすくなります。
2.情報収集のチャネルを決定する
次に、情報収集のチャネルを決定しましょう。
前述のとおり、VOCを収集できるチャネルはさまざまで、チャネルごとに特徴があります。収集したい情報をもとに、適切なチャネルを選択することが重要です。
ただ、目的ごとに利用するチャネルが分かれているわけではありません。むしろ複数のチャネルを利用することで、目的に合致するVOCを収集できる可能性がより高まります。情報の精度を上げるためにも、いくつかのチャネルの併用を検討するとよいでしょう。
3.データを収集する
チャネルが決まったら、実際にVOCのデータを収集します。
データを収集する際には、ツールやシステムを導入すると効率の良いVOC分析が可能です。ツールには、コールセンターなどの電話の音声をテキスト化してくれる音声認識ツールや、アンケートの作成、集計、分析を行うアンケートツール、大量のテキストデータから目的の情報をピックアップしてくれるテキストマイニングツールなどがあります。
これらのツールを上手に利用し、分析に役立てましょう。
4.データを分析し、活用する
VOC分析においては、収集したデータを分析し、さらに活用することが重要です。得られた大量のデータによる分析結果をもとに、必要に応じて業務や商品、サービスを改善しましょう。
よくあるのが、データを収集や分析が完了した時点で「VOC分析が終わった」と納得してしまう状態です。しかしVOC分析の真髄は、分析結果を活用することにあります。当初、明確にした目的に沿って、業務改善のポイントを洗い出しましょう。
VOC分析における注意点
VOC分析を行うにあたっては、いくつかの注意点があります。VOC分析の注意点を解説します。
1.ひとつのチャネルにこだわりすぎない
VOCを収集するとき、ひとつのチャネルにこだわりすぎないことが重要です。複数のチャネルを併用することで、より多くの情報を収集できるためです。
また、チャネルによってユーザー層が違うことにも注目してください。一般的にはSNSならば比較的若年層が多く、コールセンターに電話をかけてくるのは比較的年齢層の高い人たちが多いでしょう。ひとつのチャネルだけに頼ると、情報が偏る可能性があるため気をつけなければいけません。
2.結果をうまく施策に活用する
VOCは、分析しただけでは意味をなしません。分析した結果をうまく施策に活用することが大切です。
そのためには、そもそもVOC分析を進める前にしっかりと仮説を立てて、施策を検討しておくことがポイントです。分析結果を仮説と照合し、目的にあったかたちで施策を講じましょう。
3.PDCAサイクルを回す
VOCを分析して施策を講じた後は、しっかりとPDCAサイクルを回しましょう。
PDCAサイクルとは「Plan、Do、Check、Action」つまり、計画、実行、評価、改善の4つです。実際に行った施策について効果を検証し、さらにVOCを参考にしながら改善点を見つけ、次なる計画を立てる必要があります。
顧客のニーズは常に変化することを理解し、PDCAサイクルを途切れることなく回すことが大切です。
VOC分析が向いている企業の特徴
では、VOC分析を実施した方が良い企業とは、どのような企業でしょうか。以下のケースにあてはまるなら、この機会にVOC分析の実施を検討してみてください。
1.顧客の声を有効活用したい
顧客の声を有効活用したいと考えているなら、すぐにでもVOC分析を始めましょう。VOC分析では、顧客の声をデータ化できます。このデータは企業の資産になるものです。商品やサービスを、より良い方向へ向かわせるヒントをくれるでしょう。
2.自社の課題を解決したい
VOC分析では、外部視点を取り入れられるのも特徴です。すなわちVOC分析によって、自社が把握できていない課題に気づける可能性がある、ということです。自社の課題を洗い出し、解決したいと考えている企業も、VOC分析の実施に適しています。
3.リピーターを獲得したい
顧客の声を分析することで、リピート購入の障壁となっている要因や、逆に顧客が高く評価している点を特定できます。特に「もう一度利用したい」と思わせる決め手や、「二度と利用したくない」と感じさせる要素を把握できれば、リピート率向上のための具体的な施策につながります。
4.顧客満足度を向上したい
数値的な満足度調査だけでは見えてこない、「なぜ満足したのか」「何に不満を感じたのか」という具体的な理由をVOC分析で明らかにできます。顧客の言葉から直接的に改善点を発見できるため、的確かつ効率的に満足度向上施策を実施できます。
まとめ
VOC分析は、顧客の声を目的に応じて収集・分析するだけではなく、分析結果に基づいた施策をもって企業の目的に役立てることです。施策を行った後は効果を検証し、さらなるVOC分析で向上を図る必要があります。
また大量のVOCは、緻密に解析することで初めて、改善点の発見にもつながります。アンケートや問い合わせログ、レビューサイト、SNSなど、大量のVOCを分析するには、テキストマイニングツールの利用がおすすめです。
AIを搭載したテキストマイニングツール「見える化エンジン」
VOCを活用するなら、テキストマイニングSaaSツールでシェアNo.1を獲得している「見える化エンジン」がおすすめです。生成AIを活用したVOC自動分類機能を新規搭載し、定性データからペルソナを生成できるAIインタビュー機能のほか、アンケート調査、インタビュー調査、ソーシャルリスニングなどを効率よく実施できる機能も備え、効果的なデータ活用を強力に支援します。累積顧客導入数は1,600社以上で、手厚いサポートと、専門の分析コンサルタントによるコンサルティングを受けられます。
VOC分析に関するノウハウも蓄積していますので、VOCを分析して施策に繋げたい方は、ぜひ資料請求/無料デモ体験/お問い合わせをご検討ください。
13年連続テキストマイニングSaaS市場1位の分析ツール「見える化エンジン」はこちら
見える化エンジン「VOC自動分類」機能の詳細はこちら
関連資料:顧客体験フィードバック情報の全社活用